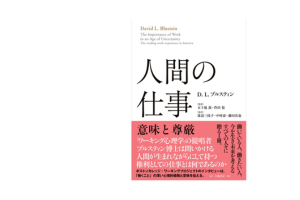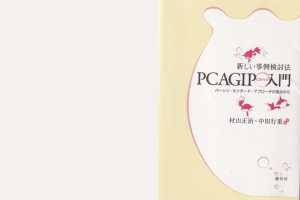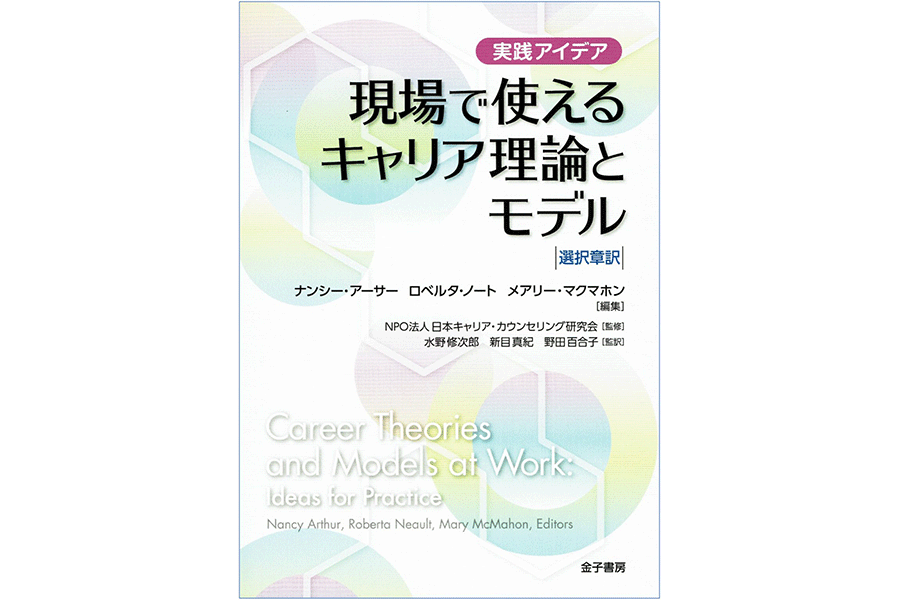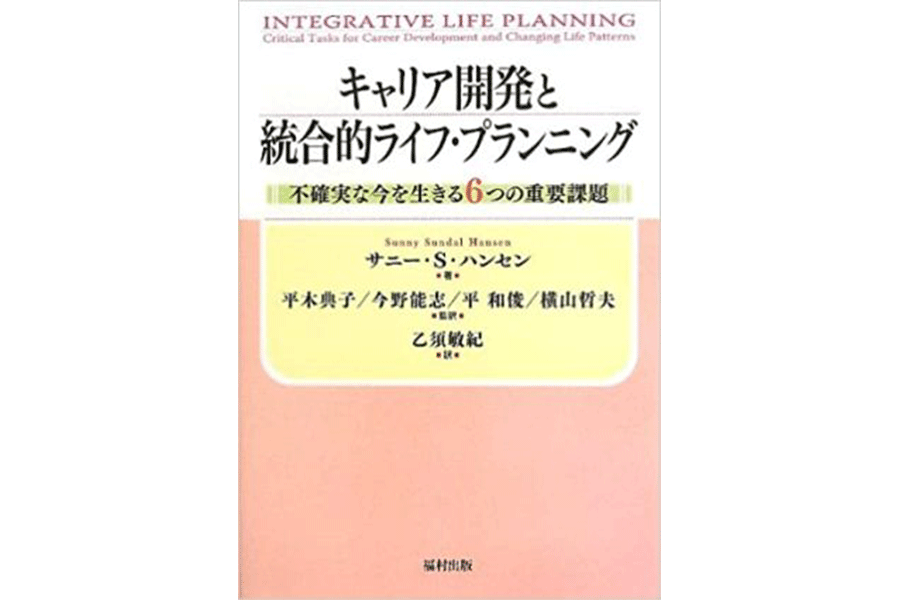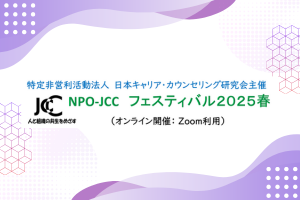これからの時代を充実したものにするために、産業界あるいは教育界でキャリア・カウンセリングの重要性が認識されるようになってきました。これからの日本社会を予測するとき、組織においても個人においても「自立」がキーワードになり、「個」が生きるキャリア開発の実践が緊急の課題です。
その基盤となるのがキャリア・カウンセリングですが、日本における実践と研究はまだ始まったばかりです。キャリア・カウンセリングは、社会の変化に対応して柔軟に変化していかなければならない領域でもあり、基本となる理論や哲学、技法の開発、カウンセラーの養成、ネットワークによる交流など重要な課題を克服しながら普及・啓蒙活動を進めていくことが求められています。
日本キャリア・カウンセリング研究会は、現在キャリア・カウンセリングに従事している方や研究している方、あるいはこれから活動に携わろうとしている方々の研鑚と情報交流の場を作るとともに、キャリア開発とキャリア・カウンセリングの普及・促進を図ることを目的として発足しました。私どもの趣旨にご賛同いただける方はぜひご入会いただき、わが国におけるキャリア・カウンセリングの普及・発展活動にご参画ください。
JCCの概念・倫理要綱
JCC日本キャリア・カウンセリング研究会の基本理念
私たちJCC会員は ワーキングライフ上のキャリア開発に関し、
- 内的キャリアを重視し、個人主導の意思決定上の支援をする
- 個人と組織の新たな共生を追求する
- キャリア・カウンセリングの研究・普及・教育などの活動を通じ、個人・組織・社会の変革をファシリテート(促進)する
JCC日本キャリア・カウンセリング研究会の倫理綱領
前文
日本キャリア・カウンセリング研究会(以下JCCという)の理念に共感・賛同し、会員となっている私たちは、この理念に基づいて共に活動できることを喜びとします。
私たちは、会員それぞれの関わり方に応じて、全員が何らかの役割を担う中で、常にこの理念に基づいて、自己決定・自己責任を前提とした行動をとります。
しかし、JCCの活動が他者(個人・組織・社会)との関わりをもつとき、そこには社会的責任が生じ、JCC会員として行動する共通の枠組みを持つ必要があります。
ここに私たちは、前提となる基本理念を基に、JCCの活動指針とJCC会員の行動基準を規定し、JCCの倫理綱領とするものです。
JCCの活動方針
JCCがキャリア開発にかかわる研究会として、JCCの基本理念に従い個人、組織、社会への活動を行う際の指針とする。
1.JCCは、キャリア開発に関し、内的キャリアを重視し個人主導の意思決定上の支援をする。
キャリアは一人ひとりの個人に属し、その個人が主導する意思決定の連鎖によって開発されるが、JCCは、 特にそれぞれの個人の内的キャリアを重視する。
個人が自己理解を深め、内面から自らを動機付けるものに気づくこと、キャリアのゴールとなる目標の設定、個別の課題解決、環境への働きかけに至るまで、キャリア開発活動となる個人の意思決定に対し、キャリア・カウンセリングをはじめ、さまざまなプログラムを開発、提供するなどの支援活動を行う。
2.JCCは、 キャリア開発に関し、個人と組織の新たな共生を追求する。
組織の中で働く個人のキャリアは、個人と関係する組織との新たな共生(相互尊重・相互依存・相互選択)において実現できる。組織の原点には、自己実現を目指している個人が居ることを理解し、その基盤の上にキャリア開発活動の研究や具体的活動に対する提案など、個人と組織の双方の新たな共生に貢献する。
3.JCCの活動を通じ、個人・組織・社会の変革をファシリテート(促進)する。
JCCは、キャリア開発活動を研究する高い専門性と、強い使命感を持つ組織として、その活動を通じ個人・組織・社会の変革をファシリテート(促進)する活動を行う。
4.JCCの活動は、常に法令を遵守し、健全な良識と倫理に基づくものである。
キャリア開発支援活動は、対象となる個人のプライバシー、関係する組織の社会的責任と深くかかわっている。JCCの活動は、良識に裏打ちされたものであり、法令遵守はもちろんとして、個人への守秘義務、企業の機密保持など、守られるべき権利を尊重する。同様に、JCCの保有する知的財産権については、許可なく使用し、または使用されることのないよう、公正な活用と保護を図る。
5.JCCの活動は、個人・組織・社会の変革に結びつける日常の研鑽・努力の積み重ねである。
キャリア開発支援活動の環境は、社会の進歩、変革に応じて時々刻々と変化している。JCC会員は、その変化に対処できる能力を身につけるため、日ごろから研鑽を怠らず、その成果を個人にとどめるものではなく、組織としてのJCCに成長をもたらし、ひいては関係する個人・組織・社会の変革に結びつけるよう努力する。
JCC会員の行動基準
1.人間への信頼
JCC会員の行動は人間への信頼を基本とし、基本的人権を尊重し、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分などにより差別を行わず、常に内的キャリアを理解する態度を持って、キャリア開発の支援活動を行う。
2.絶えざる自己研鑽
JCC会員はキャリア開発支援に関するスキルを習得し、資質の向上を図るため、絶えざる自己研鑽に努め、 高度の専門能力と資質を身につけ、JCCの更なる成長、発展、充実に寄与するよう努める。
3.個人と組織の新たな共生
JCCは、キャリア開発活動を研究する高い専門性と、強い使命感を持つ組織として、その活動を通じ個人・組織・社会の変革をファシリテート(促進)する活動を行う。
4.組織への働きかけ
JCC会員のキャリア開発支援活動が、企業、組織への働きかけに及ぶときは、関係者の問題意識が理解できるだけの知識、学識、見識を持つように努めるほか、有識者のネットワークを活用できるよう、平常からの情報収集を怠らないよう努める。
5.権利の尊重
JCC会員はキャリア開発支援の活動を通じて、個人、企業、組織の名誉を損なう行為や損害を与える行為をしないよう、相互の信頼関係を保持するよう努める。JCCの保有するシート、図表などの知的財産権については、明確な目的と意識を持って、自らこれを保持する。
6.支援関係
JCC会員はキャリア開発支援行為について、目標、範囲などの十分な説明を行い、理解を得るよう努める。 また、キャリア開発支援行為に関連して、社会通念に悖る(もとる)関係を持たない。
7.守秘義務
JCC会員はキャリア開発支援の活動を通じて、個人、企業、組織の名誉を損なう行為や損害を与える行為をしないよう、相互の信頼関係を保持するよう努める。JCCの保有するシート、図表などの知的財産権については、明確な目的と意識を持って、自らこれを保持する。
8.誠実性
JCC会員は自己の能力の限界を自覚し、能力以上の仕事を引き受けない。そのため、常に他の分野の専門家とのネットワークを持ち、必要に応じて他の分野の専門家の協力を得て、専門家の紹介や委嘱を行うよう努める。
9.行動の基準の遵守
JCC会員はこの行動基準に則って行動するものであり、日本キャリア・カウンセリング研究会の名誉を傷つけた場合は、公正な審査を経て、除名を含む相当の処分を受けることがあることを認識する。